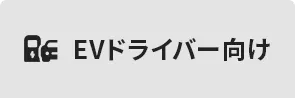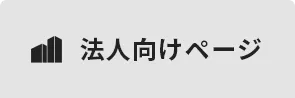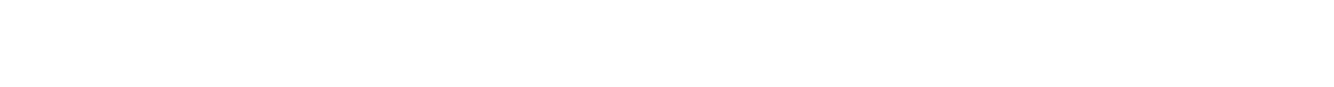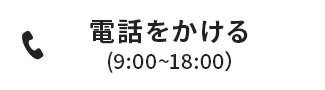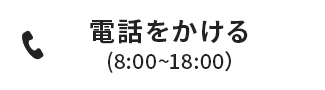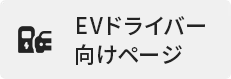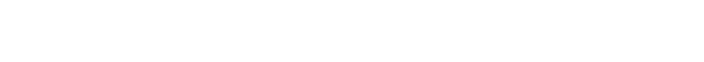[EV充電導入事例]内子町(愛媛県)
-
社名
内子町役場
-
施設名
町内8カ所の公共施設
-
業種
役場・公共施設
-
都道府県
愛媛県

画像提供:内子町
愛媛県のほぼ中央に位置し、2005年1月1日に、旧内子町、旧五十崎町、旧小田町の3町が合併して誕生した内子町は「町並み、村並み、山並みが美しい持続的に発展する町」という将来像を掲げたまちづくりに取り組んでいます。今回は、EV充電エネチェンジを導入した詳しい経緯や今後の展望について、内子町役場 環境政策室の西岡さま、亀岡さまにお話を伺いました。
今回導入いただいた施設

・内子町役場本庁(2口)
・内子町役場 内子分庁(4口)
・内子自治センター(4口)
・五十崎自治センター(2口)
・内子運動公園(4口)
・城の台公園(4口)
・龍王公園(3口)
・町並駐車場(4口)
伝統的な町並みと自然を満喫できる町
亀岡さま
かつて内子町はハゼノキの実を蒸して絞り、冷やして固める「木蝋(もくろう)」で栄えた町で、その当時の面影を残す白壁造りの伝統的な町並みがきれいに残っています。通りには、古い民家を利用したおしゃれなカフェや手仕事のお店などが立ち並び、歴史を感じながらゆっくり散策を楽しんでいただけます。
町の中心部を少し離れると、棚田や木造の屋根付き橋など、美しい里山の風景が広がっています。特に「小田深山」は、紅葉や新緑の季節がおすすめ。小田地域にはスキー場もありますので、冬にはスキーを楽しんでいただくこともできます。
特産品としては、ブドウや梨、柿などの果樹栽培が盛んなので、道の駅「内子フレッシュパークからり」や観光農園にぜひお越しいただいて、新鮮な果物をお買い求めいただければと思います。
五十崎地区で毎年5月5日に開催される「いかざき大凧合戦」も迫力があって面白いイベントです。中学生が100畳の巨大な凧を揚げる挑戦をしたりするんですよ。凧糸に「ガガリ」と呼ばれる刃物をつけて糸を切り合うという、かなり独特な戦いが繰り広げられるので、ぜひ来ていただきたいですね。
観光客の方々は、車で来られる方が多いです。公共交通機関だけでは移動が難しい地域のため、町民の方々も一家に一台どころか、一人一台に近い自家用車を所有しているのが現状です。お遍路さんですと、内子町は札所がない区間にあたるので、長期滞在よりは通過点となることが多いかもしれません。

画像提供:内子町

画像提供:内子町
EV充電器導入の検討のきっかけは?
西岡さま
内子町のEV関連の取り組みは、2023年3月に脱炭素戦略を策定して、ゼロカーボンシティを宣言したことからスタートしました。その中で、EVの導入推進も重要な取り組みの1つとして進めていこうということになったんです。2023年度に入って、複数の事業者から制度の説明や提案などをいただき、比較検討し導入を進めることになりました。
数ある事業者の中からミライズエネチェンジを選んだ一番の理由は、電気代の還元がある点です。加えて、充電アプリだけでなく、自動車メーカー各社の充電カードも使えるという点も決め手になりました。
町内をEVが走っている姿はまだそれほど多くないですが、利用者の多い公共施設に設置させていただいたところ、設置工事の段階から「いつから使えるのか」といった問い合わせが複数あり、需要を再認識しました。特にイベントなどで町外から来られる方は、EVの利用率が高い傾向にあると感じています。
導入にあたってのやりとりは非常に丁寧で、不明な点もわかりやすく説明していただき、検討はスムーズに進みました。
町民のみなさんと一緒に歩む、脱炭素へのプロセス
亀岡さま
EV充電器の設置を通して、町民の方々が「脱炭素」というものを考える1つのきっかけになればと思っています。ゼロカーボンシティの実現には、自治体だけががんばるのではなく、町民の皆さんと連携していくことが不可欠です。
正直なところ、町民の皆さんの中には、「ゼロカーボン」とか「脱炭素」と言われても、町が何をしているのか、個人として何をしたらいいのか、まだピンとこない方もいらっしゃるでしょう。私自身も環境政策室に着任して間もないので、まだまだ勉強中なのですが、個人でできることはたくさんあると思っています。たとえば、ゴミを減らす、食品ロスをなくす、節電する。それと同じようにEVに乗り換えるというのも大きな脱炭素の取り組みの1つです。「自分に何ができるんだろう」と考えていただけたら、町としては非常に嬉しいですね。EVで内子町に来られる方にも安心して来ていただいて、それが観光振興にもつながればとも考えています。
子どももおとなも楽しみながら学んでいく
西岡さま
環境への取り組みとして、新たにEVを購入する際の補助制度も2024年度から立ち上げました。EVに限らず、ゼロカーボンシティを目指すということ自体を、もっと皆さんに身近に感じてもらうための「ビジョンマップ」を作成しています。これは、脱炭素化された未来のビジョンと、そうでないビジョンを見比べて、「ここがこう変わっている」という間違い探し形式になっているんですよ。楽しみながら学習できるツールとして活用しています。間違いのアイデアも、ワークショップの中で町民の方々から募っています。
このビジョンマップは、小中学校や高校、それからおとなの団体向けのワークショップで活用していまして、少しずつ取り組みを広げていけたらと考えています。最新のビジョンマップでは間違いが10個あるんですが、高校生の中にはすべて見つけられた例もあるんですよ。
これらの取り組みを通じて、「町並み、村並み、山並みが美しい持続的に発展する町」という将来像の実現に向けて、これからも積極的にまちづくりを進めていきたいと考えています。

画像提供:内子町